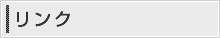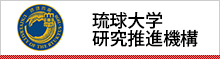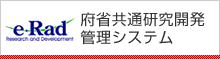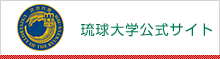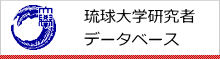Q&A
Q1 利益相反マネジメントの対象事項及び基準に該当しなくても申告が必要か?
→ 定期申告の対象者は、産学連携活動等の有無にかかわらず、その旨を申告する必要があります。未提出者と区別するためにも必ず提出してください。
Q2 全職員が対象か?
→ 常勤の役員及び職員が対象です。平成23年度から、定期申告においては、常勤の役職員のうち、役員並びに教員(附属学校教員は除く)、技術職員及び教務職員が対象となります。原則として、非常勤職員は対象外です。ただし、非常勤研究員、特命教員及び特命研究員等非常勤の研究者は対象となります。
※事務職員、看護職員及び附属学校教員(以下、「事務職員等」という)については、定期申告に関してのみ対象外としています。ただし、事務職員等であっても、本学における利益相反の審査対象であることに変わりはありませんので、産学連携活動等の状況が発生すれば、年間通して随時、自己申告し審査を受ける必要があります。【自己申告実施要領第2条第1項、第4条第3項】
Q3 全教職員対象ではなく、自己の状況を自己判断で提出させてはどうか?
→ 大学として、利益相反を適正に管理することは重要です。そのために本学におけるマネジメントの基準を設定し全教職員を対象として実施する体制を構築しました。本学及び役職員の社会的信頼を確保するため、ご理解願います。
Q4 親族(配偶者並びに父母及び子)の勤める会社等についても申告が必要か?
→ 会社員として企業等に勤務しているだけであれば不要です。但し、申告者と産学連携活動等がある企業等に、配偶者並びに父母及び子が「役員、顧問、相談役等」に「就任」している、「企業、団体の経営」に「関与」している、等の状況があれば申告してください。
【自己申告実施要領第3条第1項第2号】
Q5 同一組織からの年間の合計収入が100万円を超えない場合も申告が必要か?
→ 100万円未満であれば申告は不要です。「無」(100万円を超える収入は無いという意味)と申告してください。(未申告との区別になります)
【自己申告要領第3条1項第1号】
Q6 弁護士資格を持つ実務家教員は顧問料の収入について申告が必要か?
→ 金額については、同一組織から年間の合計収入が100万円を超えるなら申告してください。団体名、活動内容、活動時間(時間/月)については、その団体の「経営に関与」していれば、たとえば、「顧問」に就任するなどしていれば、団体ごとに申告してください。
【自己申告要領第3条1項第1号・第2号】
Q7 申告時点で研究の予定(計画)をしている場合も申告が必要か?
→ 研究の「予定」があれば、申告してください。【自己申告実施要領第4条第2項】。
Q8 国や県等の公共団体からの受託研究等の場合も申告が必要か?
→ 企業だけに限らず、公共団体からの収入等も申告対象です。【自己申告実施要領第3条第1項】
Q9 臨床研究実施者以外も、利益相反マネジメントの対象か?
→ 臨床研究でなくとも、利益相反は発生し得ます。利益相反マネジメントは、臨床研究の際の人命尊重のみを目的とするのではなく、その目的はもっと広く、(バイアスを可能な限り排除することによって)研究の真実性を担保することです。
Q10 職員の利益相反について問題になった場合、大学側がリスクを負うのか?
→ 利益相反は大学や研究者等の社会的信頼を損なうだけでなく、教育・研究活動の質を低下させる可能性もあります。大学職員が大学の業務に関連する活動の中で利益相反状態にあるにも関わらず、適切な管理を行わずに問題が発生した場合、大学としての管理責任が問われる可能性があります。本学が社会からの期待にこたえ、社会貢献活動等を通じた地域連携・社会貢献という使命を果たしていくためには、適切にマネジメントする必要があります。
なお、故意または重大な過失によって利益相反状態を申告せず、大学に損害を与えた場合、懲戒処分や損害賠償請求の対象となることもあります。
Q11 自己申告実施要項第3条に記載されている企業とは公企業も含むか?また団体はNPO法人も含むか?
→ いずれも含みます。
Q12 (1)医療法人や社団法人も実施要領第3条の「団体」に含まれるのか?(2)これらの「団体」からの寄附金も申告対象か?(3)これらの「団体」から受け取る診療報酬はどうか?
→ (1)含まれます。(2)対象です。(3)診療報酬は、申告対象ではありません。【自己申告実施要領第3条第1項第1号】
Q13 産学連携活動に係る受入については、200万円を超える共同研究、受託研究が対象との理解でよいか?
→ 共同研究、受託研究だけでなく、寄附金や機器の提供等も対象となります。【自己申告実施要項第3条第1項第4号】
Q14 同一外部組織から受入れる金額「年間200万円を超える」基準について
→ 本学では、文部科学省の「21世紀型産学官連携手法の構築にかかるモデルプログラム」及び徳島大学が作成した「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」を参考に、同一外部組織から年200万円以上と設定しております。ただし、この金額以内であれば社会的制裁を受けないことを保証するものではありません
Q15 研究室等(講座・分野等)で受入る寄附金については、教員の個人的所得にならないが報告が必要か?
→ 申告が必要です。研究室等への寄附の場合は、特に研究者の指定がない限り、寄附金受入れ及び予算管理上の代表者となっている当該研究室等の長が全て申告してください。
Q16 兼業も寄附金、共同研究、受託研究等については教授会で報告しており、大学へ届出てもいるが、申告が必要か
→ 申告が必要です。利益相反マネジメントでは、まだ大学で把握していない予定の情報、また、兼業と寄附金以外にも産学連携活動に係る相手先との関係や、申告者の配偶者並びに父母及び子に係る情報についても申告が必要です。
Q17 情報の利用、開示について。
→ 法令上要求されて拒否できない場合を除き、外部公開せず、かつ利益相反マネジメント以外の目的には使用いたしません。さらに、5年間の保管期間(規程第28条等)経過後は廃棄します。
情報の開示請求を受けた場合は、まず、情報の開示を回避できるよう請求者に対し、利益相反マネジメント担当者が確認、調整を行い、それでも開示要求がある場合は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に従って対応します。